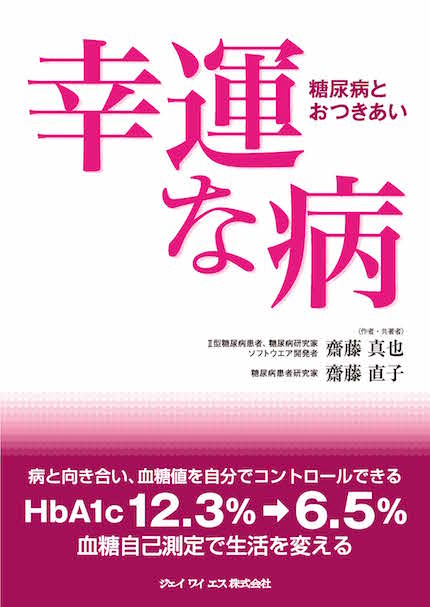父母のための栄養学(3)禍福は糾える縄のごとし
母は、2014年12月24日に腰を痛めて、立って歩けなくなった。
台所仕事が出来なくなったので妻と僕が毎日食事を作って持っていくようになった。
腰を痛める「原因を作ったと母が思っている人」が家に遊びに来ると「人を助けて我落ちる」と言い、その人を責める。
僕は、それ(せっかく遊びに来てくれた人を責める事)は、「いけない事」と思っていた。
決してその人が本当の原因ではないと言い聞かせても、納得しない。
年老いたことや10年以上前に車にぶつけられたことなどたくさんの要因があって今の状態が有るのだと思えないことが残念だった。
昨日は、週一回の父母の家に行って、一緒に食事を食べる日だった。
食べながら、こんなことを言った。
腰をいためたおかげで、「僕が毎日食事を作るようになって良かったじゃないか」と。
今度その人が来たらお礼を言ったらどうだろうと提案した。なにか、母の表情が明るくなったようなきがする。
食事を創りだしてから1ヶ月立つのだが、両親共に血色が良い。
先週くらいから「薬飲むの止めようか」というようになってきた、
かかりつけのお医者さんは飲まなくていいというのに、無理に薬を出してもらっているのだ。
うんこも形があるものが出てきている。
「うんこが変だから、写真とってもらいたい」と母が言っているということで、写真をとった。
今までは、完全に水の状態か硬くて出てこないかった。
前から食物繊維が足りないからもっと食べるようにと言っても、食生活は変えられないから、駄目だった。
父も便秘がひどかったが、最近はいいようだ。
食物繊維の重要さは昨今の栄養学では常識である。
しかし、母の育った食環境は「いかに子どもを太らせるかの栄養学」だった。
その食習慣はなかなか変えられない。
母の作る食事は、ある時期から「ひき肉をバターで炒め、さつま揚げとキャベツと玉ねぎを少々入れて卵でとじる」おかずがメインとなった。
咀嚼(ほとんど歯がない)の為にそんな食卓になるのだが、あまり好ましくないと思っていた。
しかし、変えることは困難だった。
食事は難しい。
作る手間やコストを考えながら、細胞が求めているものを用意しなければならない。
高度の技術の問題である。そして自分の経験の中からしか技術は学べない。
僕が年老いた時、子供達がそばに居てくれるだろうか?僕が父母に作っている様な食事を作ってもらえるだろうか?共に生きることが出来るだろうか?
口癖のように、「お前に手間かけてもすいわけないから死にたい」と言う母に、僕はこんな話をする。
「あなたは僕の30年後の姿なのだ、未来の僕をいたわるように接しているのです。
僕は、あなたに育てられたのだから、なんでもしても当たり前。
きっと、子供達が僕にお返ししてくれる。」と。
母は少し納得してくれた。
自分の体の状態は不便だと感じているだろう。
しかし、私達は死ぬまで自分の体と付き合っていかねばならない。
いつまでも若くてピンシャンしていたら、それはそれで困る。
子どもは、いつか老人となり、いつか引退して、新しい世界がやってくる。
新しい世界がより多くの人々を幸せにすることを信じている。
「世界」は常に矛盾や不公平を生む。それは「ヒト」の持って生まれたものでも有る。
そして「そんな世界」を変えていく力も同じものである。
いつまでも「老人」が世界を支配してはならない。
果たして子供達はこの地に帰ってくることが出来るだろうか。
「百年しばた」で僕が活動しているの問題だ。
人は必ず老いて、体がきかなくなる、そしていつか死ぬ。
幸せな人生とはなにかいつも考える。
543717